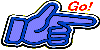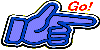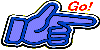
|
| 経済の研究No.101 |
| 小口株主の優待制度 |
株主優待制度はご存じですね。株主だといろいろな特典で優待されるというアレです。「経済の研究」では、第80回の補足1でご紹介しました。「四季報」か「会社情報」の企業データに「優待 有」と書いてあれば、巻末付録に優待の詳細が書かれています。株主優待は、配当以外の方法で株主に利益還元を行うことが主目的ですが、優待を通じて企業認知度を上げて貰う狙いがあります。企業認知度が向上すると株主数が増え、人気を伴って株価が上昇する利点があります。
近頃、株主優待を始める企業が増加しています。店頭公開企業が増えてユニークさが求められていることも理由ですが、1992年には250社だったものが、1998年には500社を越えています。優待を行う企業が増えるのは良い傾向ですが、株主間で不平等が生じるなど弊害が指摘され始めています。
■ どんな株主優待があるのか
株主優待にはいろいろありますが、まず人員輸送(陸海空運)企業の無料切符や無料パス、料金割引チケットがあります。自社サービスを積極的に利用させることが狙いで、株主に自社を認知して貰えるメリットがあります。一般に無料切符や系列施設利用券は小口株主(売買単位程度保有の株主。定款により1,000株、100株、1株)以上の全員が対象です。無料パスは相当数の株式を保有する大口株主となる必要があります。
次に娯楽施設運営会社が発行する招待券や優待券があります。映画館・遊園地・野球場・競馬場などいろいろあります。こちらも自社サービスを利用させることが狙いで、小口株主の優待はもちろん、大口株主にもグレードや枚数での優待があります。
また買い物券や食事券があります。スーパーや百貨店の買い物補助券(通常1割引き程度)があり、保有株数に応じてチケットが支給されるものの、通常1万株程度で頭打ちに成っています。食事券の場合は小口株主以上に一律支給である場合が多いです。
ほかには、共通商品券・図書券・プリペイドカードなど金券を配布する企業があり、小口株主以上に一律支給であることが多いようです(ジャンボ宝くじというのもあります)。あるいは自社製品や地元特産品を贈る場合もあり、カタログから選択させる場合と企業指定の場合があるようです。最近は話題性を狙って、本業と全く関係のない優待を実施している企業も増えています。
■ 株主優待は非課税の配当金
株主優待にもコストが掛かるため、配当の一種と見なすことができます。ただし優待分は、配当金とは違って、所得税ほかの課税対象になりません。金券の場合はチケット屋で高率の換金を受けることが可能であり、配当との違いが明確でありません。
人員輸送企業の場合は、常に一定の空席があるため、格別のコストが掛かりません。施設利用券や招待券も同様です。自社限定の買い物券の場合は原価割れをしない水準ですし、食事券もコストを吸収できる程度です。問題とすべきは換金性が高く、自社と無関係なサービスを提供する場合です。金券は自社以外のサービスに利用されるにも関わらず、コストだけ掛かります。共通商品券や共通飲食券も自社で使用されるとは限らないので、同様です。例えば東京小僧寿司は、ジェフグルメカード(飲食店共通食事券)12,000円分を年2回支給し、年10円の配当も継続しています。1,000株株主は年間34,000円の配当を受けている計算になります(750円の株価では利回り4.5%)。
■ 割を喰うのは大口株主
企業業績が低迷すると減配や無配となりますが、株主優待は業績と無関係に支給されることが多いようです。優待の権利取りを狙った小口株主が株式を投げ売りし、株価下落や株主数減少を招くことを怖れるためです。上記の東京小僧寿司は3期連続の赤字ですが、優待も配当も継続しています。発行株式の30%以上が経営者一族の保有株であることと関係が深そうです。
大口株主も持株数に応じて優待を受けられるので有れば公平になります。しかし、前項で指摘したように、大口株主には不利になるような優待制度が採用されることが多いので、大口株主は割を喰うことになります。それでなくとも、株主総会の案内や優待券の送付などの小口株主当たりの経費は均等で掛かっており、大口株主はかなりの部分で不利益を被っています。
国際企業の場合、外国人持株比率は高く、しかも大口株主である場合が多いです。しかし外国株主(外国国籍の個人株主、外国に登記されている法人株主)の場合、株主優待の多くは受けることができませんから、不公平を生じます。オリックスはNY市場への株式上場に伴い、株主優待制度の廃止を決断したほどです(決断しなければ外国株主の批判が集まったでしょう)。
■ 結局は株主総会対策
株主優待制度は株主総会対策に過ぎないと考えています。小口である個人株主は優待権利取りで期末ギリギリに株式取得に動いたりするので、期末株価を底上げする作用が働きをします。期末の株価安定は総会に望むに当たって好ましいことです。また優待に満足する株主は長期間保有を続けて安定株主となる可能性も高いところです。何より個人株主は、配当と優待さえ保証すれば株主総会に興味を示さないことが多く、議決権を委任するなど、経営陣に取っては有利に働きます。
同じ例ばかりを引いて恐縮ですが、東京小僧寿司では配当の継続を望まない安定株主があると思います。明らかに株主資本を取り崩しており、組織再編やリストラに使うべき資金が流出しているからです。大口株主である経営者一族は、優待制度を活かせませんが配当で潤っています。個人株主は優待と配当が貰えるウチは貰ってしまおうと考えているようです。配当のみ継続で有れば、少なからず株主から批判が出るでしょうが、現状では優待にも満足しているようです。
いくら優待制度にメリットがあるといっても、小口株主も無配と引き替えに経営再建を要求するべきなのです。その上で、経営判断にミスが有れば経営者の経営責任を問うのが本来の株主の立場です。いくら配当や優待を貰えても、あくまで自分の権利を取り崩しているに過ぎないのですから。企業が立ち行かなくなって株券が紙屑に成れば、一番に困るのは株主です。しかし小口ばかりがいくら結集しても力になりませんし、そもそも特定株主が過半数を占めていれば意味のない行動ではありますが・・・。
本来は業績が安定し、利益も十分に計上し、配当を支払いつつ内部留保を蓄積すれば、株価は継続的に上昇するものです。株価が安定上昇を続ければ、自ずと安定株主は増加します。業績が安定する限り株主総会で異議が出ることはなく、常に情報開示を継続すれば総会屋などに付け込まれる心配もありません。優待制度などで耳目を集めて大盤振る舞いをする前に、するべきことはたくさんあるはずです。開かれた経営、開かれた株主総会を志向することから始め、不透明な優待制度は廃止するべきです。業績が好調で、尚かつ本業にプラスに働く株主優待制度なら続けるべきですよ。
99.03.20
|
補足1
#N度で目立ったのが、銀行による株主優待金利制度です。足利銀行,京葉銀行などが株主の預金には店頭表示金利に若干の上乗せ金利(0.5%程度)の金利優遇をするというものでした。実際は預金を集めるための口実に過ぎませんが、足利銀行は枠一杯販売できたそうなので、株主もそれなりに気持ちをくすぐられたのでしょう。
99.03.21
|
補足2
外食のすかいらーくグループであるジョナサンは、定期株主総会で株主優待にと始めた懇親パーティを縮小すると発表しました。従来は株主1人当たり同伴者2名までの出席を認めていましたが、年々規模が膨らんできたことから、株主本人のみを招待することにしたそうです。しかし本人のみだと出席するメリットを感じない株主も多いと見られ、株主優待のデグレードが心配ですね。
昨年3月の株主総会では1,600人の出席申し込みがあり、当日は1,300人もの参加を得たということです。また株主総会には、同伴者をオブザーバという形で出席させ、盛況であったようですが、会場が混雑したというクレームが多かったと報道されています。懇親会を抽選方式にすれば良いような気もしますが、せっかく6,300人にまで増やした株主ですから、あまり邪険に扱わない方がよいでしょう。
00.04.08
|
補足3
ネットトレード大手の某証券で、信用取引と現物取引を組み合わせた「株主優待のウラ技」を伝授したそうです。魅力的な株主優待や高配当を期末に出す銘柄では、権利が確定した翌日(権利落ち日)以降に株価が大きく下がるケースが多いです。そのため、現物買いと同値で信用売りをしておいて、権利落ち後に現物渡しで信用売りを解消すれば、あまり損をせずに株主優待が受けられるというものです。
例えば、200万円の現物株1株を買い、200万円の信用売りをしておくということです。売りと買いに手数料が発生しますが、最近のネットトレードは手数料が安いのであまり問題になりません。通常こういう銘柄は、期末に向けて株価が急騰しますので、180万円で現物株1株を仕込んでおけば、利ざやも期待できます。リスクは期末の業績下方修正ぐらいでしょうか。
気を付けるべきは、配当の高い銘柄は避けた方が良いということです。現物株に貰える配当は20%の国税+地方税が天引きされますが、信用売りでは配当全額分を持って行かれます。つまり税金だけ損をします。株式分割を伴う場合も注意が必要です。巧く計算しないと損が拡がります。
さて、上記の例ではオリエンタルランド株を推奨したそうです。ディズニーランドのペアチケットを狙ったのでは、手数料とトントンという厳しさでしたが、新しいアトラクションの開業前招待券を当て込んだ個人投資家が多数飛びついたそうです。あまりの人気に、信用売りの株式が不足して逆日歩(株を借りてくるための金利。日割り計算されます)が大幅に発生して、思わぬ損失が出たとか・・。
お奨めは、低迷している映画興行会社の株主優待です。値段が手頃で、無配であったり、浮動株が多いため損をしにくいメリットがあります。優待券をチケット屋で換金すると結構な金額になります。もちろん自分で利用すれば、もっとお得です。
01.04.29
|
  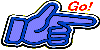
|